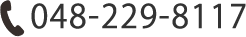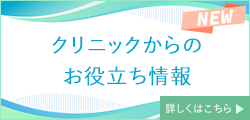リハビリテーションの内容
北戸田ナノ整形外科泌尿器科クリニックではリハビリ専門職である理学療法士(PT)によるリハビリテーションを実施しております。
理学療法士(PT)とは・・・

理学療法士は国家資格であり、リハビリテーションチームを構成する医療従事者です。
解剖学・生理学・運動学を基礎として、運動機能と動作を治療する専門家です。
- 怪我や病気によって障害をおった方の日常生活基本動作(寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなど)の改善を目指します。
- 痛みの軽減、関節可動域の拡大、筋力強化など運動機能に直接働きかける治療を行います。
- 動作改善に必要な技術を用いて、動作練習や歩行練習などの能力向上を目指します。
- 怪我や障害のリハビリテーション(リハビリ)だけでなく、スポーツにおける動きや姿勢の改善によるパフォーマンスの向上、怪我の予防などに貢献できます。
- 痛みなく自立した日常生活を送れるよう全力でサポートします。
当院には、様々な運動器疾患に対応すべく専門的知識・技術を持ち合わせた理学療法士(PT)が多数在籍しております。
ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。
当院のリハビリ(理学療法)はどんなもの?
当院のリハビリは、医師による診療と並行して行うことで治療の効果を高めます。
当院では、次のような理学療法(運動療法・徒手療法・物理療法など)を組み合わせて、痛みを和らげ身体機能の改善を図ります。
運動療法とは?
整形外科クリニックで行なわれる運動療法※として、以下のようなものが挙げられます。
- 筋力トレーニング
- 関節の曲げ伸ばし(可動域訓練)
- 筋肉のストレッチング
- 治療体操・エクササイズ(姿勢や身体の使い方の適正化、筋肉の活性化を図る。例:ピラティス)
- 生活や職業、競技などに必要な動作の練習や再学習
- 手術後やギプス固定後に行われる体重支持や荷重練習 など
これらをホームエクササイズとして紹介し、ご自宅で行なって頂くこともあります。
※『運動療法』の範疇に、理学療法士等が実施する<関節可動域運動>、<リラクセーション手技・マッサージ等>を含む場合もありますが、当院ホームページではそれらを『徒手療法』として別に説明していますので、ここでは『運動療法』=理学療法士による支援を受けながら患者さんが主体的に行なう治療エクササイズとしてご説明します。

例えば筋力をつけるためには、誰かに筋肉や関節を動かしてもらったり、外部からの電気刺激で筋肉を収縮させるだけでは不十分です。
自身の脳・神経からの指令で収縮が起こり、そこに適切な負荷がかかることで筋力が向上します。
整形外科の患者さんを悩ませる痛みについても、自ら動くと筋肉のポンプ作用によって血流が改善するため、組織の酸素不足が解消され、炎症や痛みに関係する化学物質も取り除かれやすくなって痛みの緩和が期待できます。
運動すると骨や筋肉が丈夫になるだけでなく、様々な臓器や脳の活動を刺激し、認知・心理・精神面にまでおよぶ健康増進効果が得られることがわかっています。
反対に痛みなどをきっかけに身体を動かさないでいると、さらに全身の機能が低下していく危険性があります。
当院では、徒手療法や物理療法と組み合わせながら、安全で有効な運動療法の提供に努めております。
これによって速やかな症状改善と再発予防を図り、運動機能・生活機能の向上につながるよう、支援させて頂きます。
徒手療法とは?

理学療法士が直接、患者さんの体に触れて行う手技です。
曲げにくかったり、伸ばしにくい関節の動きを改善したり(※関節モビライゼーション)、柔軟性の低い筋肉を伸ばしたり(※ストレッチ)、こわばっている筋肉を柔らかくしたり(※マッサージ)する際に用いる手技のことです。
他にも関節の安定化や神経の動きをスムーズにするといった方法があります。
関節の動きの制限や筋肉の痛み、しびれなどの症状は患者さんごとに違います。
我々、理学療法士がそれぞれの状態に合わせた方法を選択し、症状の改善を目指します。
※関節モビライゼーション
骨折後のギプス固定や疼痛による不動の期間が長いと、関節周囲の組織が硬くなり拘縮(こうしゅく)という関節の動き悪くなってしまう状態になります。
膝で起これば正座ができない、五十肩であれば腕が挙げにくいといった日常生活にも影響が出てきます。
この拘縮の改善のために行うのが関節モビライゼーションです。
関節内の骨の動きの改善や、関節を包む組織である関節包(かんせつほう)を伸ばして動きをスムーズにするために行います。
※ストレッチ
関節の動きが悪くなる原因に、筋肉の柔軟性の低下も関係してきます。
太ももの裏の筋肉(ハムストリングス)やお尻の筋肉の硬さがあると腰痛の原因にもなったりします。
その改善のために筋肉を持続的に伸ばし、少しずつ筋肉を柔らかくしていくために行います。
※マッサージ
痛みがある動きを避けようとすることで筋肉に余計な力が入ってしまい、筋肉がこわばってきます。
それが筋肉のコリやハリにつながります。血液循環が悪くなり、より筋肉のこわばりが強くなったり、痛みが引き起こされてしまいます。
こわばってしまった筋肉をもみほぐすためにマッサージを行います。
物理療法とは?

温熱、寒冷、音波、水、電気などの「物理的なエネルギー」を人体に与えることによって生じる生体反応を治療に応用したものです。
治療のみならずリハビリテーションの効果を高めるものとしても使用されます。
物理療法機器での主な効果は、以下の3つです。
| ① 鎮痛効果 | 痛みの軽減 |
|---|---|
| ② 機能改善効果 | 筋肉の緊張を緩和させる 関節の動きを改善する |
| ③ 組織再生効果 | 筋肉、骨、靭帯などの組織の治癒を促進する |
さまざまな物理療法がありますが当院では、牽引療法、電気刺激療法、超音波刺激を主に取り入れています。
当院のリハビリテーションの流れ
医師の診察にてリハビリの必要性があると判断された患者様はリハビリテーション室へご案内致します。
当日リハビリができない場合は、後日のご予約をお取りします。
1. 理学療法士による問診・身体機能評価
問診では、担当する理学療法士が患者様の症状の程度や出現しやすい動作、生活習慣、お仕事の環境など、症状の関連性を把握していきます。
身体機能評価では、関節の動き、筋の柔軟性、筋力、姿勢、歩き方、身体の使い方などを確認します。
問診と身体評価から、痛みなどの症状の原因を明らかにします。
2. リハビリプログラムの決定・実施
問診・身体機能評価をもとに患者様に適切なリハビリプログラムを行っていきます。
患者様のご希望に沿うようにプログラムを変更することも可能です。
3. 自主トレーニング・今後の治療計画の提案
患者様の症状・お身体の状況を考慮して次回リハビリまでご自宅で行って頂くと効果がある運動をご提案させていただく場合があります。
頻繁に当院のリハビリに通うことができない患者様には効果的な自主トレーニングをご提案いたします。
また、学校やお仕事の都合、ご家庭の事情も考慮しながら、患者様の痛みの程度や症状に応じてリハビリに通う頻度や1回のリハビリ時間をご提案します。
4. 次回予約
リハビリ終了後にご都合に合わせて次回のリハビリ予約をお取りします。
5. 再評価
2回目以降来院時に理学療法士が患者様の症状や身体機能を確認して、リハビリプログラムの見直しを行います。
リハビリは繰り返し行うことで効果を発揮します。このため、40分間のリハビリを週に1~2回通われる患者様が多いです。